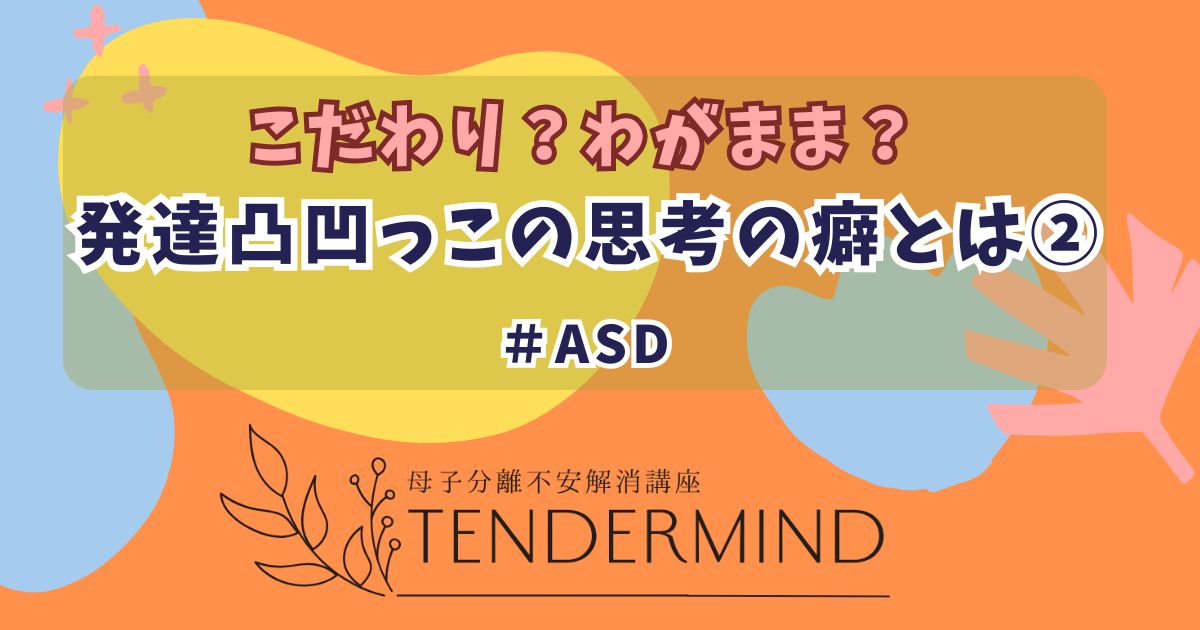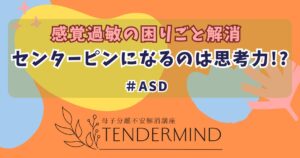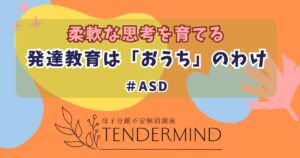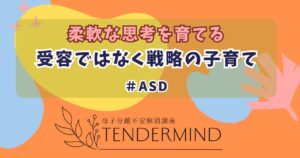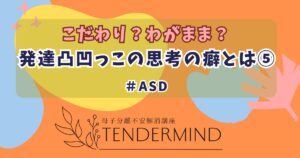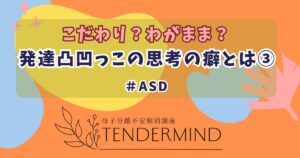いつも子育てお疲れ様です![]()
発達凸凹な母子分離不安っ子の
柔軟な思考をおうちで育てる専門家
玉中ともみです![]()
前回に続いて「思考の癖」について紹介していきます![]()
私の息子は
こだわりが強い・融通が利かない・自分のルールを曲げない
というところがあり、
「まだ小さいから」「子どもだから」![]()
と自分に言い聞かせ、何とか付き合いながらの子育てをしていましたが、
そのこだわりはどんどん強くなり、小学校に上がったのに
癇癪も手を付けられないほどに…![]()
思考の癖とは?
今回もデビッド・D・バーンズの「10項目の認知の歪み」から
③つ目と④つ目について解説します。
①②については以前の記事を読んでみてくださいね
③マイナス化思考
例えば
「褒めてもらったけど、裏があるんじゃないか?」
「上手にできたけど、偶然」というように
本来ポジティブに捉えられるような出来事もネガティブに変換してしまう
ということです。
この思考があると、自己肯定感をつけたり成功体験をつけてあげたり
ということがとても難しくなってしまいます![]()
本やネットで調べた方法も通用しないことが多いのです![]()
④結論への飛躍
ちょっと注意した時に「ママはもう僕なんて嫌いなんだ!」
なんてことはありませんか![]()
この思考も正しい接し方をしなければ思考の癖が強化されてしまいます。
転んでしばらく足が痛かったりすると→「もう歩けなくなる!」
と思ってしまうように自身を苦しめるものになってしまいます![]()
“注意をされること”は学校など外の社会では多くあること…
そのたびに「嫌われた」と考えてしまうことで
不登校や学校への行き渋り、
更には精神疾患に繋がってしまうのです![]()
「思考の癖」に苦しむのは誰よりも子ども自身です![]()
近くで子どもの思考の癖に付き合うママも同じように
辛い思いをしてしまうことになります![]()
色々な書籍を読んできた、ネットでも検索した
という真面目で子どもを大切に思っているママほど
まずは子どもに「思考の癖」がないか![]()
気付いてほしいと思っています![]()
子どもに柔軟な思考力をつけられるのは、
やっぱり近くで子どもと毎日コミュニケーションできるママなんです![]()
自己肯定感も、成功体験も
「思考の癖」を改善していくことでついてきます。
特別に専門的な勉強をするわけではなく、
必要なのは親子のスムーズなコミュニケーションです![]()
子育てを楽で楽しいものに変えていきたいですね![]()